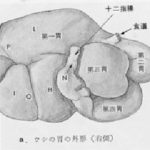昭和30年台の集乳事情
昭和30年代当時、使われた原料乳は細菌数の多い質の悪いものでした。生乳には多くの雑菌が含まれていました。農家は搾乳時間になると牛をつないで、お湯に浸した布で乳頭を拭いて、手でバケツに生乳を搾っていました。それを牛乳缶と呼ばれる鉄製の容器に詰めて、井戸水や川の水で冷やしながら集荷を待ったそうです。牛乳は10℃以下で貯蔵しないと細菌が増殖してしまうので、腐敗や酸化が進んでしまうからです。当時は、搾乳保管された牛乳缶を、保冷機能のないトラックの荷台に積んで集荷施設や牛乳工場に運び込むのが一般的な方法でした。もちろん、というか残念ながら、集荷場にも搾乳した生乳を冷蔵する保管設備などありませんでした。
そのうえ、道路も現在のような舗装の行き届いた道ではなかったので、牛乳工場に届くまでは相当な時間が掛っていたようです。今では考えられないですね。当然ですが、炎天下の夏などには腐敗が進みやすくなります。また時間が進むにつれて、酸化が進んでしまうことも問題でした。
森永ヒ素ミルク中毒事件が日本の牛乳を変えた
こうした事情の中で事件は起きました。なぜ猛毒のヒ素が赤ちゃんが飲む粉ミルクに混入してしまったのでしょうか。当時、生乳の酸化の進行を止めるために乳質安定剤(酸化防止及び酸度安定剤)として過酸化水素のほか第二リン酸ソーダが大量に使われていました。乳製品の凝固を防ぎ、溶解度を高めるために触媒が使われていましたが、それに粗悪な工業用のヒ素化合物を使っていたためにで、出来上がった粉ミルクにはヒ素が残ってしまい、中毒症状が起きました。当時の厚生省の発表によると、死亡者130人、被害者数12,344人で、表に出なかった数も相当あると見られています。史上最大の食中毒事件と言えるでしょう。
当初は奇病扱いされていましたが、1955年に事件として発覚しました。翌年の厚生省の発表で先ほどの被害者数が発表されました。ところが、当時は高度経済成長が優先され、満足のいく救済措置はとられなかったそうです。日本政府も森永側にたって収束を測ったため、被害者の運動は抑え込まれてしまいました。
その14年後に大阪大学医学部が指導した人の活躍によって、被害者に後遺症が残っている可能性があぶりだされて、事件は再燃しました。そのことにより裁判闘争と不買運動が盛んになり森永に過失を認めさせることになったのです。
森永が中毒の原因をミルク中のヒ素化合物と認めたのは事件から15年後のことでした。当時、森永乳業は業界トップでしたが、この事件の裁判の影響でイメージダウンは避けられれず、大幅にシェアを落としていきました。
なぜ超高温殺菌が普及したのか
森永に過失があったことは疑いようのない事実です。ですが、ここでは当時の牛乳の鮮度管理に大きな課題があったことを理解しておいて頂きたいと思います。酸化が進んだ牛乳は加熱に弱くなり、すぐに凝固して使い物にならなくなるそうです。凝固していない部分を牛乳にするわけですが、歩留まりが著しく低下してしまいますね。しかもできた牛乳の品質も悪くなるのは避けられません。つまりおいしくないということです。酸化が進んだ生乳でつくった粉ミルクは、お湯に解けづらくなります。鮮度がいい生乳は牛乳用として、鮮度の落ちた生乳は粉ミルクなどの原料として使用されるのが当時の常識だったからなおさらです。それで大量の乳質安定剤を使っていたわけです。一部理解できますが、とても飲料とは思えないような処置をとっていたのだなと思ってしまいますよね。
ですが、事件後は当然のことながら乳質安定剤の使用は厳しく制限されるようになりました。乳質安定剤を使えなくなった代替法として超高温殺菌の導入が注目されたのです。超高温殺菌では高い割合で熱に強い細菌も死滅させてしまいます。このため、腐敗や酸化が進みにくくなり賞味期限も伸びるメリットがあります。もちろん乳酸菌などの有用な微生物も死滅させるデメリットもあります。
現在は酪農家で搾乳された生乳はバルククーラーという冷却装置で瞬時に4℃以下に冷却されます。集乳車も冷却設備がありますし、道路網も当時とは比較にならないほど整備されています。低温殺菌ではなく、高温殺菌法が98%も占めているというのは乳業会社の効率を優先したいという事情に偏っている気がしてしまいます。
牛乳や乳製品に限らず、自分たちが口にしているものに対してもっと関心を持ち、納得できる選択をしてほしいと思います。消費者のことを考えない当時の森永のような態度には不買運動を通して、NOを突きつけなければなりません。それがメーカーに改善させる大きな動機にもなるのです。
「価格じゃなくて、価値で買う」、私のメンターの教えです。価格に見合った価値があるかないか、きちんと判断したいですね。安さの裏に愛する我が子の生死が掛かっているような製品は買いたいとは思えません。